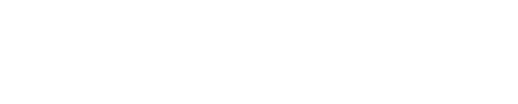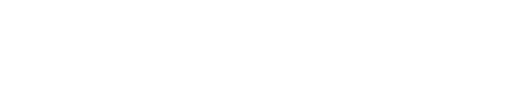よくある質問
後遺障害について
-
後遺障害申請の認定結果に納得がいかない場合は?
労災保険の給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求(不服申し立て)をすることができます。
ただし、審査請求(不服申し立て)を行うためには、労働基準監督署の決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査官に対し、審査請求(不服申し立て)をする必要がありますので、時間的余裕がなく、早期の対応が必要です。
改めて審査請求(不服申し立て)のための証拠収集も必要となりますので、後遺障害申請の認定結果に納得がいかない方は、できる限り早くプロスト法律事務所にご相談下さい。
-
労災保険の後遺障害認定について教えて下さい。
症状固定時に後遺障害が残った際には後遺障害申請の手続きをとる必要があります。労災保険から後遺障害等級(1~14級)が認定された場合に支給される「障害(補償)給付」は、後遺障害等級によって受け取れる金額が大きく違います。特に、後遺障害等級1級~7級が認められた場合、継続して年金を受け取ることができます。
また、労災保険により認定される後遺障害等級は、会社等に損害賠償請求を行う場合にも重要な基準となります。
労災保険に対する後遺障害申請では、適切な後遺障害等級を獲得することが極めて重要です。
そのためには、必要な検査や画像撮影の実施、医師の意見書の取り付けなど、十分な医学的証拠を揃えることが必要です。
適切な後遺障害等級獲得のため、医学知識豊富なプロスト法律事務所にご相談下さい。 -
症状固定(治ゆ)とは何ですか?
労災保険では、労災による傷病が「治ったとき」まで療養(補償)給付が行われ、傷病が「治ったとき」に身体に残った後遺障害に対し、障害(補償)給付が行われます。
この「治ったとき」とは、身体の組織が健康時の状態に完全に回復することではなく、「医学上一般的に認められた医療行為を行っても、治療効果を期待できなくなった状態」のことを指し、この状態のことを労災保険では治ゆ(症状固定)と呼びます。
損害賠償請求について
-
労災の損害賠償請求に期限はありますか?
労災の損害賠償には、消滅時効(一定期間権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる法制度)が定められていますので注意が必要です。
会社等への損害賠償請求には、会社等の安全配慮義務違反による債務不履行を理由とする請求と、会社等の不法行為を理由とする請求の2種類があります。
債務不履行の場合、権利を行使することができることを知った時から5年、または、権利を行使することができる時から20年で消滅時効が完成します。(民法166条1項、同167条)
不法行為の場合、損害及び加害者を知った時から5年、または、不法行為の時から20年で消滅時効が完成します。(民法724条)
なお、民法改正に伴う消滅時効の見直しの関係で、債務不履行責任については、2020年4月1日以前の事故の場合は、事故から10年間で消滅時効が完成します。
-
労災について、会社等に対して責任を問い、慰謝料などの損害賠償は請求できますか?
労災の発生について、会社等に不法行為もしくは安全配慮義務違反が認められる場合には、会社等にも直接損害賠償請求ができます。
労災保険による補償は、治療費と休業損害、後遺障害逸失利益などの一部にとどまるため、慰謝料や逸失利益の残額など、労災保険により補償されない部分は会社等に対し損害賠償請求をすることとなります。
会社等への損害賠償請求を行う際には、安全配慮義務違反や損害の発生を証明する必要がありますので、労災保険の調査内容や認定が重要な証拠となります。労災発生から損害賠償金の請求まで、専門家による一貫したサポートが重要です。
その他の質問
-
長時間労働による脳・心臓疾患の発症の場合、労災保険の給付は受けられないのでしょうか?
厚生労働省は、過労等による脳・心臓疾患の発症について基準を設けており、この基準で業務上の疾病として認められた場合には、労災保険の給付が受けられます。
当該基準では、「発症直前かつ前日までの異常な出来事」「短期間の過重業務」「長期間の過重業務」等から評価します。
この「過重業務」の認定について、「発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できる」などの具体的な労働時間の基準が設けられており、労災認定の一つの目安となります。
このため、長時間労働による脳・心臓疾患の発症が疑われる事案では、被害者の労働実態を解明し、当該基準を満たした過労状態にあったことを証明することが重要となります。
-
正社員でなければ労災保険の給付は受けられないのでしょうか?
パートやアルバイト等の雇用形態にかかわらず、事業主との間に雇用関係があれば、正規雇用者と同様に労災保険の給付を受けられます。
労働者災害補償保険法の対象となる「労働者」は、労働基準法上の「労働者」と同様の概念であり、「事業者に使用され」「賃金を支払われる」関係にあれば「労働者」に当たります。
このため、請負契約や委託契約の場合でも、労働条件や勤務状況によっては、労災保険の給付を受けられる可能性があります。
「雇用契約がない」等の理由で会社に労災保険の使用を拒否された場合は、一度プロスト法律事務所にご相談下さい。
-
労災申請をしようとしたところ、会社が労災保険に未加入だと言われました。
会社が労災保険の加入手続きを行っていない場合であっても、労災認定されれば、労働者は保険給付を受けることができます。
労災保険は原則強制加入の保険ですので、加入手続きが未了・保険料が未納であっても、労働者を保護するため、労災保険の使用は認められるのです。
-
会社が労働基準監督署に事実と異なる報告をしているのですが、問題ありませんか?
「労災隠し」の一例として、会社から労働基準監督署に事実と異なる事故状況を報告するというものがあります。
会社は、労災事故発生後、事故の発生日時・事故状況・事故の発生原因等をまとめ「労働者死傷病報告」という書類を労働基準監督署に提出する義務があります。
労働基準監督署はこの「労働者死傷病報告」をもとに労働安全衛生法違反の調査・判断を行います。
事実と異なる事故状況・事故原因等を放置すると、会社が労災資料を責任逃れの証拠として利用し、被害者が会社の安全配慮義務違反を証明することが困難になる可能性があります。
事実と異なる事故状況・事故原因が報告されていることに気が付いた場合、すみやかに、労働基準監督署に訂正を求めることが重要です。
-
会社が労災保険を使わせてくれないのですが、どうすればいいでしょうか?
勤務先や元請け会社が労災保険関係の書類作成に協力しない場合には、会社を通すことなく、直接労働基準監督署に労災保険の利用申請を行うこともできます。
労災保険の使用に協力しない、いわゆる「労災隠し」は違法であり、犯罪です。
労災隠しは、『労災保険を使用すると会社が支払う保険料が増えたり、企業のイメージダウンになったりする』という会社の身勝手な理由のもと、行われることがあります。
業務上や通勤中の災害は労災保険の対象で、健康保険を使うと違法になりますので、労災による怪我の治療のためにも、適切な労災申請は不可欠です。